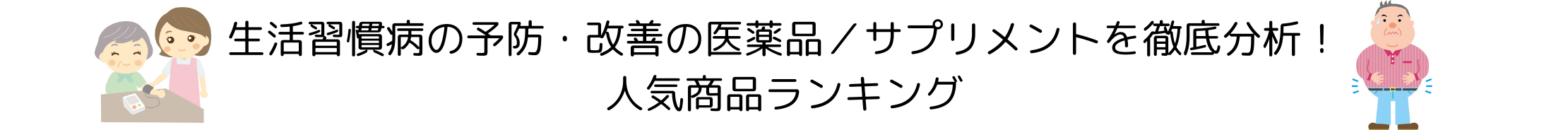生活習慣病対策 3. 医薬品・薬での治療

生活習慣病の治療の一つ「薬物治療」
糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病にかかってしまった場合、運動療法や食事療法のほかに薬物を使って治療する場合があります。
基本的に薬物治療は、運動療法や食事療法で効果が見られない場合や症状が強い場合に使われます。
薬物治療は医師による処方、指導がもとに行われるので、自分で簡単に始められるものではありません。
薬や医薬品には副作用や、症状によっては摂取してはいけない成分などが含まれている場合もあり、デメリットも理解した上で服用する必要があります。
では、生活習慣病治療の医薬品にはどんなものがあるのでしょうか?
症状別にご紹介いたします。
肥満・肥満症の治療薬・医薬品について
日本で承認されている肥満や肥満症の治療薬は多くなく、近年使われている薬は「マジンドール」と、2023年に新たに承認された「セマグルチド」という治療薬などです。
マジンドールは摂食抑制、消化吸収抑制、消費エネルギー促進などの作用があり、セマグルチドは食欲を抑える働きがある治療薬です。
ただ、吐き気やめまい、便秘、喉の渇きなどの副作用があるため、服用の際は注意が必要です。
薬以外にも、食欲コントロールやむくみ対策に漢方も使われます。
また、女性の場合ホルモンバランスによって食べ過ぎやむくみなどが起きるので、ホルモンバランスを整える医薬品も肥満予防の方法の1つとしてあります。
糖尿病の治療薬・医薬品について
糖尿病の薬物治療には、7種類の経口薬と2種類の注射薬があります。
・ビグアナイド薬
・チアゾリジン薬
・スルホニル尿素薬
・グリニド薬
・DPP-4阻害薬
・グリミン
・α-グルコシダーゼ阻害薬
・SGLT2阻害薬
・GLP-1受容体作動薬
経口薬には3つの種類があります。
インスリン抵抗性を改善させるものと、インスリンの分泌に関するもの、糖の吸収を抑えたり、排泄を促進させるものです。
代表的な注射薬もインスリンです。
インスリンを打つことで、糖の吸収の働きを改善させて、糖尿病の悪化を防ぎます。
参考:南山堂「まるごとわかる!生活習慣病」 31‐32ページ
高血圧の治療薬・医薬品について
高血圧の治療に使われる医薬品は、いわゆる「高圧薬」です。
高圧薬の第一洗濯として以下の4種類があります。
・カルシウム拮抗薬
・アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬
・アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)
・利尿薬
血管を広げる薬がほとんどですが、利尿薬は尿を出すことで血液量を減らして血液を下げます。
また、心拍出量を減らす薬や血管の収縮を抑える薬などもあり、組み合わせて使用する場合もあります。
参考:南山堂「まるごとわかる!生活習慣病」 40ページ
脂質異常症の治療薬・医薬品について
脂質異常症の治療薬は、肝臓・小腸・LDL受容体へ働きかける薬になります。
以下の治療薬が選択肢として選ばれます。
・スタチン(プラバスタチン)
・小腸コレステロールトランスポーター阻害薬
・PCAK9阻害薬
参考:南山堂「まるごとわかる!生活習慣病」 50‐51ページ
肝臓のコレステロール合成を阻害させたり、LDL受容体を活発にさせることでコレステロールを低下させます。
これらの治療薬は、肝臓や小腸に刺激を与えるため、吐き気や腹痛、胃腸痛などの副作用のリスクがあります。
▼医薬品・治療薬に関するより詳しい内容は、第五章でご紹介しております。