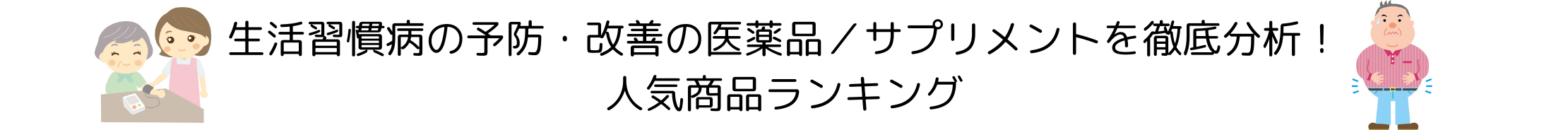生活習慣病に使われる治療薬・医薬品とは?
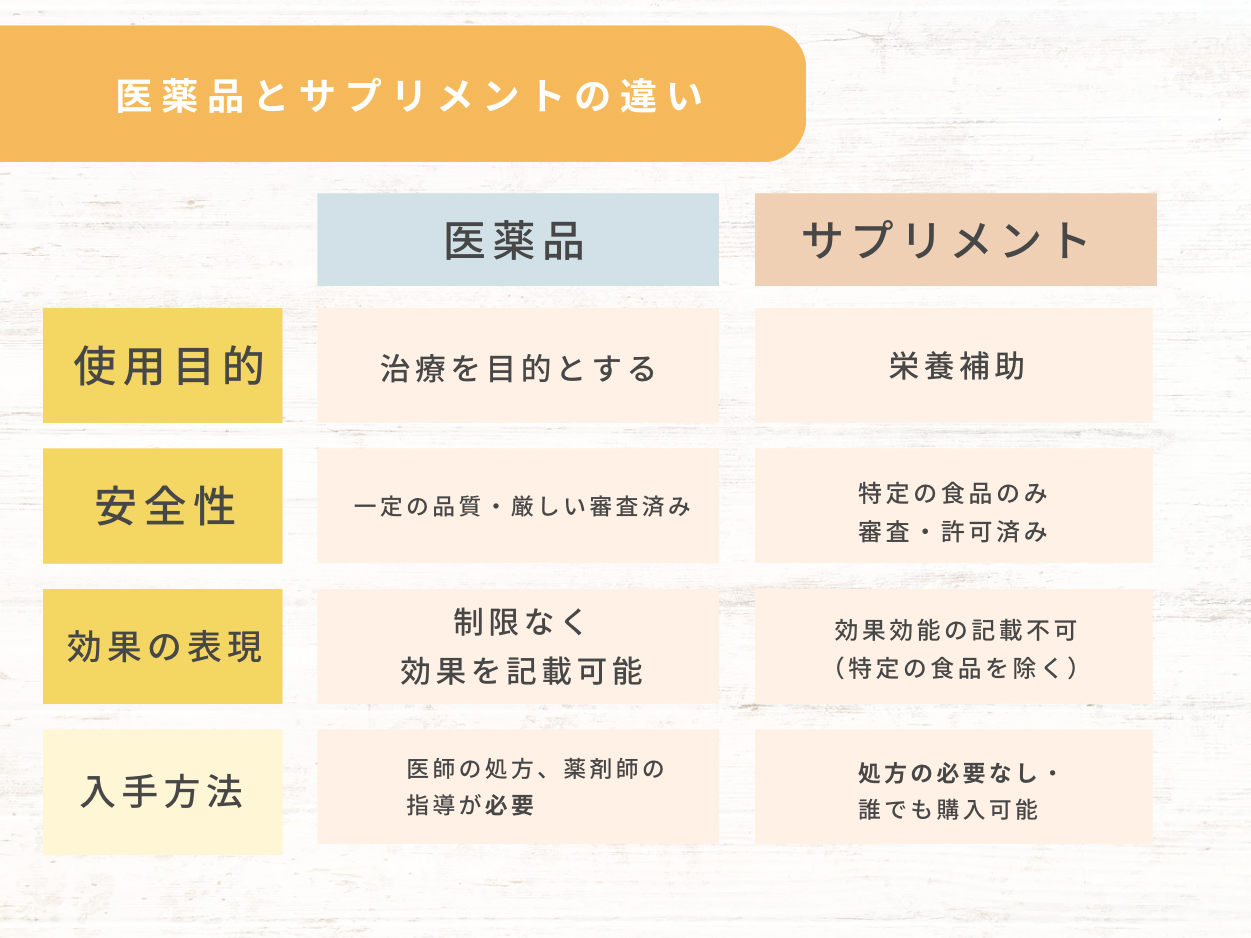
ここでは、生活習慣病予防や治療に使われる医薬品の具体的な製品や成分についてご紹介いたします。
【生活習慣病予防・治療】肥満・肥満症の治療薬・医薬品
生活習慣病の1つである「肥満」や「肥満症」の治療に用いられる薬をご紹介します。
実は、日本で承認されている肥満症の治療薬は「マジンドール」と最近承認された「セマグルチド」、漢方薬があります。
▼抗肥満薬と漢方
| 作用 | |
| マジンドール (サノレックス) | 食欲に関わる神経に働きかけて食欲を抑え、体の消費エネルギー・代謝促進により体重を減らす。 |
| セマグルチド | 脳に働いて食欲を抑える効果、胃の動きを抑える効果。 |
| 防風通聖散 | 骨格筋・肝臓でのインスリンの感受性を改善させる働き。 |
| 防已黄耆湯 (ぼういおうぎとう) | 肥満に伴う関節の腫れや痛み、むくみ、肥満症(水ぶとり)を改善させる漢方薬。水を排泄することで、体を引き締めるお薬。 |
| 大柴胡湯 (だいさいことう) | 肝臓や胃腸の病気、高血圧に伴う症状に使われる漢方薬。脂質代謝の改善、便秘の改善にも用いられる。 |
参考:おくすり110番「マジンドール」
http://www.interq.or.jp/ox/dwm/se/se11/se1190008.html
「大柴胡湯」
http://www.interq.or.jp/ox/dwm/se/se52/se5200093.html
クラシエ「防已黄耆湯」
https://www.kracie.co.jp/ph/k-therapy/prescription/bouiougito.html
治療薬は、食欲を抑える働きをして肥満を解消するものがベースとなります。
そして、漢方薬はむくみや便秘の解消による肥満へのアプローチするものが多いのが特徴です。
【生活習慣病予防・治療】糖尿病の治療薬・医薬品
では、糖尿病の治療薬にはどんなものがあるのでしょうか?
糖尿病の治療薬には、インスリンの抵抗性を改善させるもの、インスリンの分泌を促進させるもの、糖の吸収を抑えたり、排泄を促進させるものがあります。
以下、それぞれの機能ごとに治療薬をまとめているので、参考にしてみてください。
▼インスリン抵抗性改善系
| 効果効能 | |
| ビグアナイド薬 | 肝臓で糖が作られるのを抑える働き |
| チアゾリジン薬 | 骨格筋・肝臓でのインスリンの感受性を改善させる働き |
※注意点・副反応のリスク
ビグアナイド薬は胃腸障害、チアゾリジン薬は体重増加、むくみ、骨折などに注意しましょう。
▼インスリン分泌促進系
| 効果効能 | |
| スルホニル尿素薬 | 肝臓で糖が作られるのを抑える働き |
| グリニド薬 | 骨格筋・肝臓でのインスリンの感受性を改善させる働き |
| DPP-4阻害薬 | インクレチン作用を介して、血糖依存症のインスリン分泌を促進し、グルカゴンを抑制する |
| GLP-1受容体作動薬 | インクレチン作用 |
※注意点・副反応のリスク
スルホニル尿素薬・グリニド薬は低血糖、DPP-4阻害薬は便秘、GLP-1受容体作動薬は悪心、嘔吐、食欲減退などに注意が必要です。
▼インスリン抵抗性改善、分泌促進系
| 効果効能 | |
| グリミン(テトラヒドロトリアジン系) | ミトコンドリア機能改善により血糖依存的なインスリン分泌と、筋肉および肝臓での糖代謝を改善する2つの作用 |
※注意点・副反応のリスク
胃腸障害に注意しましょう。
▼糖吸収、排泄調整系
| 効果効能 | |
| α-グルコシダーゼ阻害薬 | 小腸で炭水化物の吸収を遅らせる |
| SGLT2阻害薬 | 肝臓での糖排出を促進させる |
※注意点・副反応のリスク
α-グルコシダーゼ阻害薬は腹部膨満感、SGLT2阻害薬は尿路感染症に注意が必要です。
参考・引用:南山堂
「まるごとわかる!生活習慣病」32ページ
【生活習慣病予防・治療】高血圧の治療薬・医薬品
高血圧の治療薬には降圧薬が使われます。
▼第一選択肢となる降圧薬
| 作用 | |
| カルシウム拮抗薬 | 血管を広げて、血管抵抗を減らす働き。 |
| アンジオテンシン変換酵素阻害薬 | 血管を収縮させて血圧を上げるアンジオテンシンⅡを作る酵素の働きを阻害し、血管を広げる働き。 |
| アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 | アンジオテンシンⅡが受容体と結合するのを阻害し、血管を広げる働き。 |
| 利尿薬 | 尿を出すことで血液量を減らす働き。 |
高血圧の治療にはまず、上記の4つのどれかが用いられることが多いです。
その他にも、心拍出量を減らす「β遮断薬」や血管の収縮を抑える「α遮断薬」などもあり、いろんな面からのアプローチで血圧を改善することができます。
【生活習慣病予防・治療】脂質異常症(コレステロール改善)の治療薬・医薬品
脂質異常症の薬物治療では、肝臓、小腸、LDL受容体のそれぞれにアプローチするものがあります。
| 作用 | |
| スタチン | 肝臓内のコレステロール量を減らし、血液のLDLコレステロールの量を減らす働き。高コレステロール血症の治療に用いられる。 |
| 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 | コレステロール値と中性脂肪(トリグリセリド)の低下作用。小腸でコレステロールの吸収を抑える働き。 |
| PCSK9阻害薬 | 高コレステロール血症の治療薬。肝細胞へLDLコレステロールの取り込みを促進させることで、血液中のLDLコレステロール値を下げる働き。 |
スタチンには「プラバスタチン」など、小腸コレステロールトランスポーター阻害には「エゼチミブ」、PCSK9阻害薬には「エボロクマブ」という種類があります。