第三章
生活習慣病の予防・治療・対策
〜運動や食事改善、薬・サプリメントで予防対策しよう!〜
生活習慣病の対策2 「禁煙」と「節酒」

生活習慣病で改善必須な項目「喫煙」と「過度な飲酒」
生活習慣病での中でも命に関わる大きな病気の原因の一つである「喫煙」と「過度な飲酒」。
生活習習慣病の予防・改善には、この2つをやめることが不可欠とも言えます。
ただ、飲酒に関しては禁酒する必要はありません。
適切な量の飲酒であれば大きな問題はないので、「飲み過ぎをやめる」ことを意識しましょう。
禁煙のメリット
タバコには5,300種類以上の化学物質と、250種以上の有害物質、70種以上の発がん性物質が含まれているといわれています。
喫煙をすることで収縮期血圧が約20mmHg増えるともいわれ、寿命が5分30秒縮まるという調査結果もあります。
喫煙は今すぐにでもやめることでメリットがあります。
ある研究では、60歳で禁煙すると約3年、50歳だと約6年、40歳だと約9年、30歳だと約10年の余命が延長すると考えられています。
また、家族や周りにいる人が受動喫煙することで、循環器疾患の発症リスクが高まるとも言われており、自分だけでなく周りの大切な人のためにも禁煙をおすすめします。
禁煙の効果を以下にまとめています。
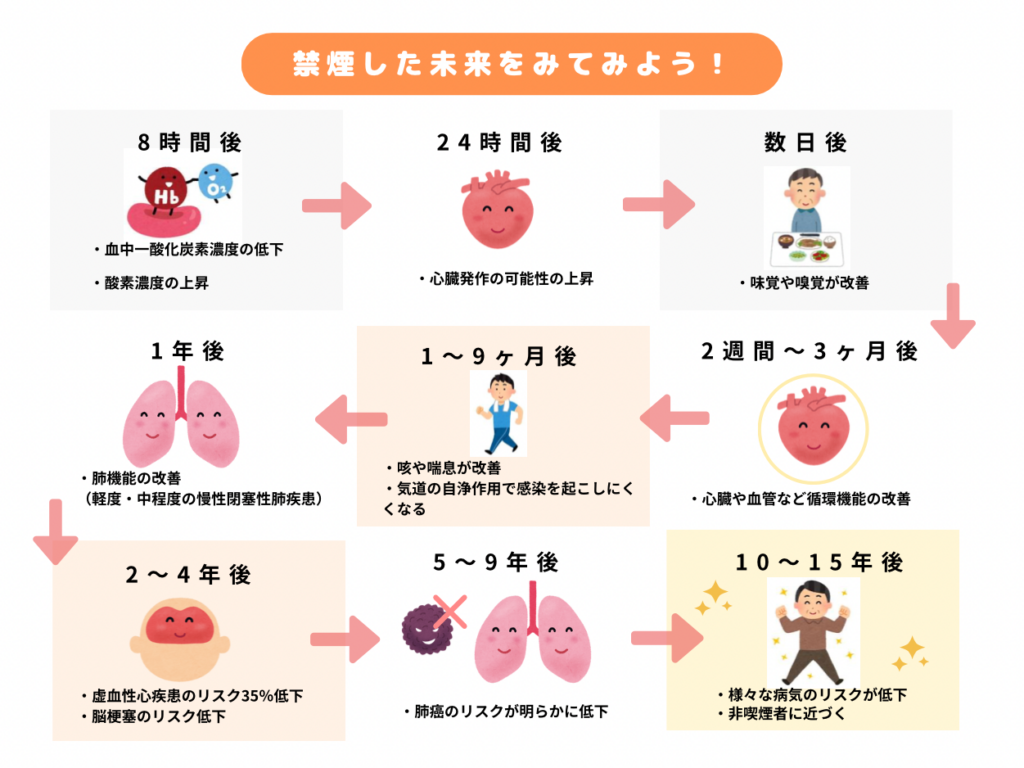
参考:南山堂
「まるごとわかる!生活習慣病」111ページ
禁酒・節酒のメリット
お酒はタバコと違い、絶対にやめなければいけない、というわけではありません。
適量であれば、血糖値を下げ、血行を良くし、疲労回復やストレス解消にも効果があります。
ただ、「飲み過ぎ」は絶対にNGです。
多量飲酒による弊害はたくさんあります。
脳神経への弊害として認知症や慢性硬膜下血腫、糖尿病神経障害、心臓への弊害として高血圧、肝臓への弊害としてアルコール性肝障害など、リスクが高い病気含まれます。
また、適量であっても毎日飲み続けるのは避けましょう。
お酒の習慣化で、アルコール中毒になってしまう可能性もあります。
節酒のメリットは、以下です。
- 検査値の改善
- 症状の改善
- 酒代が浮く
- 缶や瓶のゴミが減る
逆にお酒を減らすことで、ストレスが溜まる、飲まないと眠れないなどもあるかもしれません。
それでも、飲み過ぎによるリスク回避のためにも節酒をおすすめします。

